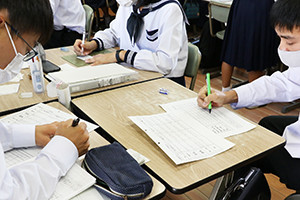SSH基礎課題研究発表(テーマ代表による発表) 2020/10/30
10月23日に決定した各テーマの代表12グループ。
10月30日(金)5~7限目、アリーナにて1年生全員に向けて12グループがスライド形式による発表を行いました。
今回、講師として次の皆様をお招きしました。
石本弘治先生(第一工業大学自然環境工学科 教授)
荻田太先生(鹿屋体育大学スポーツ生命科学系 教授)
ハフィーズ・ウル・レーマン先生(鹿児島大学理工学研究科 准教授)
塔筋弘章先生(鹿児島大学理学部 准教授)
各グループ、発表6分・質疑応答2分の持ち時間で発表。
写真下:直前まで熱心に打ち合わせを行う生徒たち。
各グループの発表テーマは次の通りです。
・黄金比は本当に美しいのか(1年1組)
・果たして双子素数は無限に存在するのか?(1年1組)
・手回し発電機を利用したエネルギー可視化実験(1年4組)
・円周率の近似と精度(1年4組)
・虫を集めよう 〜虫が集まる色を調べる〜(1年2組)
・菌の発酵について(1年1組)
・わたしと雲と天気の三角関係(1年5組)
・GREEN TEA BATH SALT 〜茶葉の新たな可能性〜(1年2組)
・音速を測ろう(1年7組)
・重力加速度を測定しよう(1年1組)
・化学反応の量的関係(1年2組)
・火山灰とよりよく生きよう(1年7組)
どのグループも緊張しつつ研究成果を丁寧に伝えました。
写真下:発表後、たくさんの質問が出ました。
最後に、石本先生から総評をいただいました。先生からは
・先行研究をたくさん調べ、理解を深めよう。
・スライドの作り方をもっと工夫しよう。
・地元ならではのテーマにも注目しよう。
など助言をいただきました。
発表を行った12グループの皆さん、お疲れ様でした。大勢の前での発表、大変だったと思いますが良い経験になったことと思います。また、同級生の発表を聴いた1年生は刺激を受けたことでしょう。
ご指導くださった4人の先生方、ありがとうございました。